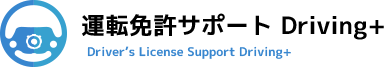あおり運転の被害に遭わないために。全てのドライバーが知るべき予防と対処法
近年、悪質な「あおり運転」による悲惨な事件が後を絶たず、厳罰化(妨害運転罪の創設)も行われましたが、依然として多くのドライバーが不安を感じています。誰もが被害者にも、そして意図せず加害者にもなり得るこの問題。一番大切なのは、トラブルに巻き込まれないための「防衛運転」を日頃から意識し、万が一の際の対処法を正しく知っておくことです。今回は、あおり運転の被害を未然に防ぐための予防策と、実際に被害に遭ってしまった際の具体的な対処法を詳しく解説します。
第1章:トラブルを未然に防ぐ「予防策」
あおり運転のきっかけは、追い越し車線を走り続ける、急な割り込みなど、些細な交通マナー違反から生まれることが少なくありません。まずは、相手を刺激しない、誤解を招かない運転を心がけることが最も重要です。
1. 常に「キープレフト」を徹底する
片側二車線以上の道路では、最も右側の車線は「追越車線」です。追い越しが完了したら、速やかに左側の走行車線に戻るのが交通ルールです。追越車線を走り続ける行為は、後続車の通行を妨げ、あおり運転を誘発する典型的な原因の一つとされています。「自分は制限速度を守っているから大丈夫」という考えは禁物です。道路全体の円滑な流れを意識し、キープレフトを徹底しましょう。
2. スムーズで予測しやすい運転を心がける
不必要な急ブレーキ、頻繁な車線変更、ウィンカーを出さずに曲がるなどの「予測しにくい運転」は、周りのドライバーを驚かせ、苛立たせる原因になります。常に周囲の状況を把握し、早め早めの合図を出すこと、一定の速度で穏やかに走行することを意識するだけで、無用なトラブルの多くは避けられます。
3. 無理な割り込みは絶対にしない
合流や車線変更の際、十分な車間距離がないにも関わらず無理に割り込む行為は、相手に急ブレーキを踏ませるなど、極めて危険であり、トラブルの直接的な引き金になります。譲ってもらった際にはハザードランプで感謝を示すなど、ドライバー同士のコミュニケーションも円滑な交通には不可欠です。
第2章:被害に遭ってしまった際の「対処法」
どれだけ気をつけていても、理不尽なドライバーに遭遇してしまう可能性はゼロではありません。もし、あおり運転のターゲットになってしまったと感じたら、感情的にならず、ご自身の安全確保を最優先に行動してください。
1. 冷静さを保ち、挑発には絶対に乗らない
相手からクラクションやハイビームで煽られても、決して対抗してはいけません。スピードを上げて引き離そうとしたり、ブレーキを踏んで威嚇したりする行為は、相手をさらに逆上させ、より危険な状況を招くだけです。「相手にしない」という強い意志を持ち、冷静さを保つことが重要です。
2. 安全を確保し、速やかに道を譲る
後続車が異常に接近してきた場合は、まず相手から離れることを考えます。安全を確認した上で左側に寄り、ハザードを出すなどして道を譲る意思を示し、先に行かせましょう。高速道路であれば、最寄りのサービスエリアやパーキングエリアに一時的に退避するのも有効です。相手はあなたを追い越したいだけかもしれません。無用な張り合いは避け、物理的な距離を取ることが身を守ることに繋がります。
3. 安全な場所へ避難し、ためらわず警察に通報する
相手が執拗に追跡してくる、幅寄せを繰り返すなど、身の危険を感じた場合は、すぐに安全な場所へ避難し、ためらわずに警察(110番)に通報してください。避難場所として最適なのは、人目が多く、すぐに助けを求められる場所です。
- サービスエリア、パーキングエリア
- コンビニエンスストアやスーパーなど、駐車場の広い商業施設
- 交番、警察署
避難したら必ずドアを全てロックし、相手が車から降りてきても決して窓を開けたり、車外に出たりしてはいけません。スマートフォンの通話機能を使い、警察官と話している様子を見せることも、相手を牽制する効果が期待できます。
4. ドライブレコーダーを設置する
これは予防策であり、同時に最大の対処法でもあります。ドライブレコーダーは、万が一の際に何が起きたかを客観的に記録してくれる、最も強力な証拠です。警察への通報時にも、ナンバーや車種、運転の状況を正確に伝えることができます。また、「ドライブレコーダー録画中」というステッカーを貼っておくだけでも、あおり運転を抑止する効果が期待できます。
まとめ
あおり運転から身を守るためには、「自分は加害者にならない」「相手を挑発しない」という予防意識と、「被害に遭ったら安全を最優先に行動する」という正しい知識の両方が必要です。運転は、道路を共有する全てのドライバー同士の思いやりで成り立っています。当スクールでは、運転技術だけでなく、こうした交通社会の一員としての心構えや、危険を回避するための防衛運転についても、講習を通じてお伝えしています。常に心にゆとりを持った運転で、安全で快適なカーライフを送りましょう。